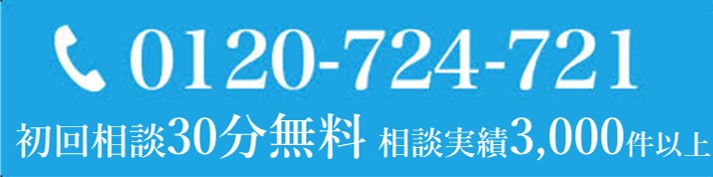男性が離婚・離婚調停を有利に進める方法を枚方・茨木の弁護士が解説
「法律相談に行ったら『離婚するときは男性が不利』『早く負けを諦めて離婚した方が良い』と言われました」といった声を耳にすることが良くあります。実際にネットを見ても、離婚は男性が不利と書かれた記事も見かけます。
ですが、本当に為す術なく女性の言うなりに離婚を進めなければならないのでしょうか。
確かに男性は、女性よりも考えるべきポイントは多く、その結果、諦めるべきところも出てくるかもしれません。ですが、主張すべき点はしっかりと主張をすることで、「一方的な離婚」「言われっぱなしの離婚」を防ぐことができるのです。
目次
- (1)忘れてはいけない婚姻費用の落とし穴
- (2)離婚調停を長引かせるメリット・デメリット
- (1)メリット
- ①納得がいくまで話し合える
- ②監護実績を積む
- ③証拠の収集
- (2)デメリット
- ①婚姻費用の支払が続く
- ②仕事を休まなければならない回数が増える
- ③精神的負担が大きい
- ④離婚訴訟へ移行
- (3)離婚調停を有利に進めるために
- (1)主張は書面でまとめる
- (2)証拠の重要性
- (3)調停期日の日の注意事項
- (4)話し合いの進め方
- (1)妻の話に耳を傾けてみましょう
- (2)協議が難航した場合
- (3)養育費
- (4)財産分与
- ①分与の割合
- ②特有財産
- ③住宅ローン
- (5)親権
- (6)面会交流
- 男性が離婚問題を弁護士に相談するメリット
- 当事務所の解決事例(クリックすると事例の詳細にアクセスできます)
- ご依頼者からのお声(40代 男性 面会交流・婚姻費用)
- 弁護士法人アイリス
- 最新記事 by 弁護士法人アイリス (全て見る)
(1)忘れてはいけない婚姻費用の落とし穴
男性が離婚に向けて活動するにあたり、最も気を付けなければならないのが婚姻費用です。
婚姻費用とは、夫婦と子供が通常の生活を維持するために必要な「生活費」を指し、夫婦の収入に応じて分担する義務があります。(婚姻費用について詳しくはこちらもお読みください>>)
婚姻費用は別居した後であっても離婚をするまでの間は支払わなければなりません。
特に、妻が専業主婦だったり、パート等収入が少ない場合や、子供が私学に行っている場合など予想以上の婚姻費用を負担しなければならない場合もあります。
逆に妻側からすれば、離婚をしてしまうと婚姻費用が受け取れなくなりますので、離婚協議が長引いても問題ないと考える傾向にあります。
むしろ敢えて離婚協議を長引かせる戦略を取ってくる女性もいます。
また、女性は今までの生活を変えなくない一心で、相場を超える高額な婚姻費用を求めてくることもあります。
男性側は、まずは婚姻費用の出費を抑えることを考えなければなりません。
請求された金額が相場の範囲内であるかどうか、相場以下の金額に抑えるような事情があるかどうかの検討のほか、先に離婚を決めることも検討してみましょう。
親権は離婚時に決めなければ離婚ができませんが、それ以外の財産分与・面
会交流・養育費といった条件は離婚をした後でも、話し合いをすることが出来ます。
(2)離婚調停を長引かせるメリット・デメリット
離婚調停にかかる期間は概ね6ヶ月~1年程度のことが多いのですが、当事者双方が話し合いを重ねて離婚条件に同意して初めて離婚が成立しますので、あともう少しのところで調整が難航して2年近くかかるようなケースもあります。
ここでは、調停が長引くことによるメリットとデメリットについてお話します。
(1)メリット
①納得がいくまで話し合える
先ほど申し上げたとおり、調停は夫婦が話し合いを重ね、2人ともが離婚条件に同意することで離婚が成立します。
ですから、養育費の額や面会交流の内容など納得が出来ない条件がある場合には、安易に同意せず、粘り強く交渉を続けることも必要です。
弁護士が就いている場合には、調停と調停の間の期間も弁護士同士で話をすることも出来ます。
②監護実績を積む
別居後あなたがお子様と生活をしている場合には、お子様の監護実績を積むことが出来ますので、親権を獲得するにあたり、それが有利に働くことがあります。
③証拠の収集
配偶者が不倫をしている場合には、配偶者が不倫をしている証拠を集めなければなりません。
離婚調停の期間中に探偵に依頼するなどして配偶者の行動を調査するなどして不貞の確たる証拠を収集できることがあります。
(2)デメリット
①婚姻費用の支払が続く
離婚が成立するまでの間、収入の多い側が婚姻費用の支払いをしなければなりません。
あなたが家を出る形で別居をしている場合には、住宅ローンを負担しながら、更に婚姻費用を支払い、ご自分の生活費も負担しなければならないことになり、経済的な負担が大きくなります。
②仕事を休まなければならない回数が増える
調停は概ね1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで平日に行われますので、出席するために仕事を休まなければなりません。
長引けば長引くほど仕事に支障が出たり、同僚や上司に離婚調停のことを説明せざるを得なくなることがあります。
③精神的負担が大きい
離婚は人生の大きな転換点となる出来事ですから、精神的負担も大きくなります。
最初は離婚に向けて勢いもあるのですが、離婚を考えている相手と何度も何度も長期に亘って話し合わなければならず、延びれば延びるほど精神的な疲れがたまりやすくなります。
④離婚訴訟へ移行
もしも調停で離婚条件が合意できなければ、最終的には調停は不成立となり、離婚訴訟に進みます。
離婚訴訟になれば更に1年近く離婚までの期間が延びてしまいます。
また、判決が出る前に法廷で証言台の前に立って相手の代理人や裁判官から質問を受けて答えなければならない尋問という手続もあります。
更に、訴訟は原則公開となっており、尋問の際には誰でも傍聴席に座って聞くことが出来ます。
これらが精神的に負担となることもあります。
このように、調停が長引くことによって得られるメリットもあるものの限定的で、一般的には、むしろデメリットの方が大きいといえます。
妥当な期間で納得できる条件をスムーズに整えていくためには、離婚の専門的な知識を持った弁護士にお任せいただくことが大切です。
離婚をお考えの方、配偶者から離婚調停を申立てられた方は弊所にご相談ください。
(3)離婚調停を有利に進めるために
離婚調停では、男女の調停委員2名と裁判官(裁判官は立会は殆どありません)が配偶者との間に入り、離婚や親権、面会交流、養育費、財産分与などについて協議を進めていきます。
調停では、待合室は別々に用意されており、交代で調停委員と話をしますので、基本的には夫婦が顔を合わせることはありません。
ここでは、できるだけ調停を有利に進めるためのポイントについてお話をします。
(1)主張は書面でまとめる
1回の調停の時間は概ね60~90分程度になることが多く、交代で調停委員と話をしますので、意見を伝える時間はかなり限られます。
当日口頭で伝えようとすると言い忘れてしまったり、十分に理解してもらえなかったりする可能性があります。
そこで、ご自身が伝えたい内容は予め書面に纏めておきましょう。
また、書面は調停期日の1週間~10日前を目途に裁判所に提出しておくと、調停の前に調停委員も書面に目を通してくれますので、次の調停期日でスムーズに話し合いが進みます。
(2)証拠の重要性
不貞の慰謝料やDVの慰謝料を請求する場合には、その証拠を収集しておくことが重要です。
収集した証拠は調停の場で提出することを検討しましょう。
調停を申し立てると相手も警戒をして証拠を揃えにくくなります。
ですので、緊急を要する場合を除いて、証拠の準備を整えてから調停を申し立てた方がいいでしょう。
(3)調停期日の日の注意事項
調停委員は中立の立場で調停を進めていきますが、調停委員も人の子です。
中立であろうとしても、無意識のうちに進め方に偏りが出てくることも否定できません。
調停委員と喧嘩腰に話をするよりは、共感して貰った方が話をスムーズに進めることが出来ますし、場合によっては相手を説得してくれることもあるでしょう。
その一方でご自分が譲れないラインは常に意識しておくことが必要です。
調停委員は話をまとめることが仕事ですから、調停の最終局面に入った時には、説得しやすい方・話を分かってくれそうな方を説得しようとすることがあります。
このような時には、ご自分が譲れないラインについてしっかりと示すことが大切です。
また、調停委員が話す内容が必ずしも正しいとは限らないことも忘れてはいけません。
調停委員は法律の専門家とは限りません。また、話をまとめることが仕事ですので、慰謝料の相場が100万円だとしても、夫が100万円しか支払わないと主張し、妻が300万円を支払うよう求めた時には、その間を取って200万円で妥協するよう求めることもあるのです。
調停委員からの提案に疑問がある場合には、焦ってその場で回答することは避けて、次回期日までの間に弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
(4)話し合いの進め方
(1)妻の話に耳を傾けてみましょう
離婚を決意することはかなりのエネルギーが必要です。
そのため、一度離婚を強く決意すると、なかなか「もう一度やり直してみよう」とは思えないことも多いのです。
「離婚なんて考えてもない」という男性の場合は、妻の夫婦関係・家族関係に対する不安や不満に真摯に耳を傾け、丁寧に問題を解決することで、妻に離婚を決意させてしまわないよう、心がけましょう。
「離婚は仕方がない」と考えている夫婦はどうでしょうか。
妻もこれまでの夫婦・家族関係に不満が溜まっている状況ですので、妻の話を無視して一方的に話を進めてしまえば、妻も意地になって一切譲歩しないこともあり得ます。
離婚協議とは、夫婦・家族についての最後の話し合いですから、妻の意見にも耳を傾けることが、逆に妻からの譲歩を引き出すきっかけにもなりますので、しっかりと妻と向き合って話をすすめてみましょう。
(2)協議が難航した場合
夫婦での話し合いがどうしても困難な場合もあります。
その結果、長期間にわたり婚姻費用を支払い続けなければならない状況に陥るかもしれません。
妻側に代理人が入っている場合には特に婚姻費用をもらい続けるメリットが説明され、話し合いがのんびりと進められてしまうこともあります。
このような場合には、男性から離婚調停や離婚裁判を起こすことも検討しましょう。夫婦の間に調整役の第三者が入ることで、話し合いがスムースに進むこともあります。
なお、調停は平日に行われますので仕事を休まなければなりませんし、また、次の調停の日までに考えなければならない宿題が出されたり、資料を提出しなければならかったりと仕事の合間にする作業が増えることがあります。
このような場合でも、弁護士に依頼することで、代わりに調停や裁判に出頭してもらったり、宿題を適切に処理することが出来ます。
離婚調停や離婚裁判など離婚の種類についてはあわせてこちらもお読みください>>
(3)養育費
女性が親権者になった場合には、男性は女性側に対して毎月一定額の養育費を支払わなければなりません。
子供のためにはできる限りのことをしてあげたいと考えている男性が殆どかと思いますが、その一方で、養育費が多額になれば、自分の生活が苦しくなる可能性もあります。
もしくは、毎月ではなく一括でまとまった養育費を支払って終わりにしたいと考える男性もいるかもしれません。
あるいは、ちゃんと子供のために養育費が使われているか、把握しておきたいと考える男性もいらっしゃることでしょう。
養育費をいくら支払うのか、その支払い方法をどうするのか、妻の口座に振り込むのか塾や学校に直接振り込むのかといった点を決めて、合意書を作成することで、その後の紛争を予防することが出来ます。
(4)財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻生活を営む間に築いた財産を分ける手続きで、
原則は夫婦がそれぞれ1/2ずつ財産をもらい受けることになります。
①分与の割合
夫婦の一方が特殊な技能を有していたり、会社を経営することで財産を多く築いたときなど、夫婦の財産を1/2よりも多めにもらい受けることが出来る場合があります。
②特有財産
財産分与の対象は「夫婦で築き上げた財産」ですので、例えば自分の両親から贈与された財産や相続財産などについては、財産分与の対象から原則は外すことが出来ます。
また、「夫婦で築き上げた財産」であれば、財産の名義は問われませんので、妻名義の財産はもちろん、子供の名義で貯めてきた預金等についても、財産分与の対象になることがあります。
③住宅ローン
婚姻中に夫名義でローンを組んで住宅を購入した場合、その家を処分するのかどうか、住宅ローンをだれが負担するのかといった難しい問題が発生します。
夫婦で組んだローンであっても、あくまでも銀行との関係ではローンの主債務者は夫となります
ですので、ローンを名義変更せずに離婚後は妻が支払いを続けることに決めても、万が一妻の支払いが滞れば、銀行は夫に支払いを求めてくるのです。
売却を考えた場合であっても、中古住宅はオーバーローン(自宅を売却してもローンが完済出来ない状態)になっていることが多いため、残ってしまった債務をだれが幾ら負担するかを決めなければなりません。
妻に残債務の半額の負担を求めるというのも、ひとつの手かもしれません。
(5)親権
親権は、子どもの年齢が小さければ小さいほど母である女性が有利と言われており、残念ながら実務でも女性に親権が認められることが多いです。
ただ、子供が大きくなってくると、子どもの意見が重視されるようになっていきますし、これまで子どもと良好な関係を築いてきた場合には、子どもが父である男性と一緒に生活することを希望し、かつ、子どもを実際に養育することが出来る環境が整っていると判断され、親権を取れることもあります。
男性は平日夜遅くまで仕事に出ていることが多く、「養育することが出来る環境」を整えることは難しいかもしれません。
ですが、どうしても親権を希望される場合には、自分が仕事している間も両親に手伝ってもらえるよう両親宅の近くに住んだり、残業をしなくても良い部署に異動するなどして、しっかり面倒をみれる環境を整備することが不可欠です。
親権をとることがどうしても難しい場合には、親権を諦めて子どもと会う機会(面会交流)をしっかり確保するよう交渉することも重要となります。
(6)面会交流
面会交流とは、子どもと一緒に住んでいない親が子どもと交流を持つことを言います。
面会交流の決め方は「月に1回程度交流する」とざっくり決める場合と、「毎月第〇日曜日の〇時から〇時まで、△△で子どもを引き渡す」等具体的に決める場合があります。
また、子どもと直接会って交流する方法のほか、手紙やメール、電話といった手段を用いて間接的に交流する方法もあります。さらには、長期休暇等の際に、宿泊を伴う面会を実施する場合もあります。
面会交流の方法や回数等を決めたら、面会交流をしっかり実施してもらえるように、合意書を作成して取り決めの内容を残しておくようにしましょう。
また、子どもを監護する母が父と子の面会を拒否して、会わせてくれないケースもあります。このような場合には、調停を起こして裁判所で話し合いの機会を設けて面会の機会を確保してもらう必要があります。
男性が離婚問題を弁護士に相談するメリット
当事務所の解決事例(クリックすると事例の詳細にアクセスできます)
妻の度重なる不貞行為を原因として妻と男性双方に慰謝料の支払いを求めた事案
ご依頼者からのお声(40代 男性 面会交流・婚姻費用)
協議離婚して半年くらい経った朝、見慣れない封筒が自宅に届きました。
それは、元奥さんが立てた代理人の先生からでした。内容は、養育費や面会の日数の件で元奥さんが調停を申し立てるので、本人同士は連絡を取らないこと。裁判所からの連絡が入るまで待っていなさい。と言うものでした。
何が起こったのかもわからず、とりあえず元奥さんに連絡しましたが、連絡は取れず…。この先どうやって子供たちと会う段取りをつけるのか?
毎回面会の度に相手の弁護士さんを通さないといけないのか?養育費はいくらになるんやろう?? など色んなことを考えて、仕事も手につかず、不安で不安で仕方ありませんでした。 何日か経ち、こちらも弁護士さんに相談しようと思い、ネットで色んな事務所を探しました。もしお願いすることになれば、話し合いも何度もしないといけないだろうし、あんまり遠くや大阪市内で探すのではなく、自宅や会社からなるべく近いところをと思い、北摂をとりあえず探しました。2~3件位弁護士事務所に相談したのですが、電話で断られていました。そしてついに出会えたのが郷原先生でした。人生初めて面と向かって話した弁護士さんです。
とにかく第一印象は、若い可愛いせんせいやなー、と思いました。色々自分の状況を説明して、先生にお願いしたところ快く引き受けて下さいました。
それから結局2年以上調停は続いたのですが、色々大変なこともありましたが、とにかく先生にお願いしてから決着がつくまでの間、僕は大体1ヶ月半に1回行われる調停と、それに向けての先生との話し合いが楽しくて仕方ありませんでした。とにかく話し合いの時は明るく楽しく喋っていただいたし、いざ調停の場ではきっちりと僕が言いたいこと、伝えたいことを伝えていただけるし、とても心強かったです。何でもかんでも聞いてくれる訳ではなく、
僕が間違った事をお願いすると、必ず分かりやすく説明して下さって、考えを改めるようにアドバイスもしていただける、人としても大尊敬できる先生です。僕は今、この文章を誰に向けて書いてるのかわからなくなってきましたが、とにかく僕は郷原先生にお願いしてとっても満足ですし、大感謝です。事務員さんも、先生不在の時など、いつも丁寧に接してくれましたし、伝言ミスなど0ですし、ほんとにお世話になりました。感謝しております。
次にまた何かあったときには必ず先生にお願いしようと思います。
ホントにありがとうございました。調停結果にも、何の不服もありませんし、満足しております